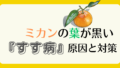完熟のトマトは美味しいですよね!
実は、ナス科の野菜であるトマトはとても連作障害に弱いんです!
連作障害は、高い確率で病害虫が発生して生育が悪化します。適切な対策を講じないと収穫量や品質が大幅に低下します。
同じ野菜でなければ連作障害は起きないと思われがちですが、同じナス科の野菜を栽培しても引き起こされます。
- ジャガイモ
- ナス
- ピーマンなど
これらは全てナス科の野菜です。

今回の記事では、同じナス科の野菜が引き起こす連作障害について詳しく解説します。
この記事からわかること

連作障害には対策があります。
原因を理解してちゃんと対策しましょう
トマトに発生する連作障害
トマトに発生する連作障害には、次のような病害虫が原因挙げられます。
フザリウム病(枯れ病・萎ちょう病)
病原は細菌が原因で主に根と茎に発生します。
土壌に残った菌が発生源であり、多発すると輪作又は土壌消毒を行う以外に対策はありません。

疫病
土壌中のカビが原因で葉、茎、果実、根に発病します。
葉に不規則円形の水が浸みたような病斑が現れ、次第に大きくなって暗褐色の病斑になります。
湿度が高い時は病斑部に白いカビが現れます。雨の多い気象条件の時に多発する傾向があり、短期的に急激にまん延していくことがあります。
症状に気づいたら対策は急務です。
センチュウ
土壌にいるセンチュウが根部に寄生することにより、根が膨れてコブ状になるネコブセンチュウと根に潜り込んで食害し、根を腐食させるネグサレセンチュウの2つの被害があります。
一般的には連作により被害を受けます。
トマトの前作に相性が悪い野菜たち
トマトと同じナス科の野菜同士(ジャガイモ、ナス、ピーマンなど)を後作で栽培すると連作障害を引き起こす可能性が高くなります。
一般的には輪作して連作障害が起きないようにします。
連作障害を回避するため、異なる種類の作物を順番に栽培する農業手法です。これにより、土壌の栄養バランスを保ち、病害虫の発生を抑えることができます。薬品を使用しない有機農法で用いられる。
ジャガイモ(ナス科)

ナス(ナス科)

ピーマン

連作障害を防ぐには
輪作
前述したとおり、輪作により連作障害を防ことができます。
異なる科の作物を交互に栽培することで、土壌の栄養バランスを保ち、病害虫の発生を抑えることができます。
例えば、
- トマトの後作 ⇒ ユリ科(ネギ、タマネギなど)
- ピーマンの後作 ⇒ キク科(レタスなど)
土壌改良
有機物を土壌に加えることで、土壌の栄養バランスを改善し、連作障害を軽減することができます。
堆肥や緑肥を使用することが効果的です。
ちなみにおススメの緑肥は『マリーゴールド』です。
マリーゴールドの根から分泌される化学物質がセンチュウに対して毒性を持ち、センチュウの繁殖を抑制します。これにより、作物の根がセンチュウの被害を受けにくくなります。
薬剤を使用しないセンチュウ対策として、マリーゴールドは大変有効です。
土壌消毒剤による洗浄
土壌消毒剤による消毒が最も一般的な洗浄方法です。
まとめ
- ナス科の代表的な連作障害(フザリウム病、疫病、センチュウ)
- 連作障害の対策は『輪作』、『土壌改良』、『土壌消毒』がある。
最後まで記事を読んで頂き、ありがとうございます。参考になれば幸いです。
ナス科の野菜は連作障害に弱い野菜なので、まずは『輪作』により計画的な作付け計画で栽培することが大切です。
また、多湿にならないよう風とおりを良くするなど家庭菜園の環境改善も大変有効です。
関連記事
- 【トマト】なぜトマト栽培後の畑がネキリムシ予防になるのか?
- 【トマト】トマトと好相性!混植すると元気になる野菜3選
- 【ナス】ナスと好相性!おススメのコンパニオンプランツ3選
- 【ジャガイモ】生育不良をサクッと解決!『ジャガイモ袋栽培』とは
- 【マリーゴールド】センチュウ対策だけじゃない!マリーゴールドの驚くべき効果

関連記事も合わせてご覧ください
楽天市場 公式広告